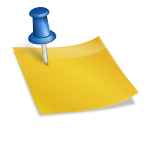「その書類、誰が作りましたか?」──税務の現場では、見えにくい一線があります。記帳代行はOK、でも“税務書類の作成・代理”は有資格者だけ。本件は、その境界を踏み越えた疑いで、82歳の会社役員が税理士法違反容疑で書類送検されたという出来事です。
舞台は長野県上田市。依頼したのは法人1社と個人2人、作成されたのは確定申告など計13通。地域で頼られてきた「総合経営相談所」の一角で、善意と実務が絡み合う“グレーの常態化”が、ある日を境に“違反の事実”になりました。
本稿では、出来事の全体像を物語として追いながら、制度の仕組み・起こりがちな誤解・実務的なリスクと対策を体系的に整理。読み終えるころには、「どこまでが記帳、どこからが税理士業務か」を、あなたのチームで即日運用できるレベルで線引きできるようになります。
- 物語的要約:地域の“お助け役”が、境界線の誤認から税理士法に抵触した疑いで書類送検へ。
- 事実データ:法人1社・個人2人からの依頼で13通の税務書類を作成(2024年1月〜2025年3月)。
- 問題の構造:記帳代行と税務代理・書類作成の区別が不徹底、組織内の業務定義と最終チェックが弱い。
- 解決策:業務範囲の明文化、委託契約の条文化、税理士確認フロー(レビュー/押印/電子提出権限)の導入。
- 未来への示唆:地方・小規模事業者ほどDXと専門家ネットワーク接続が要。地域連携で“合法の助け合い”を再設計。
2024年初頭から2025年春へ──何が起きたのか?
本件の核は「境界線」を越えたこと。82歳の会社役員は、総合経営相談所の枠内で記帳代行を請け負う一方、依頼者からの要請に応じて、確定申告などの税務書類の“作成”まで担った疑いが持たれています。
| 時期 | 出来事 | 当事者視点のメモ |
|---|---|---|
| 2024年1月〜3月以降 | 法人1社・個人2人からの依頼に基づき、確定申告等の税務書類を作成(計13通) | 「いつも記帳してる人だから任せたい」──信頼が境界の見落としに |
| 2025年・春〜夏 | 国税局が事案を把握、告発へ | 提出形跡や関与範囲の精査を受け、事案が顕在化 |
| 2025年9月10日 | 地検上田支部へ書類送検 | 容疑は認めているとされる |
すべては“善意の拡張”から始まった
地方の小規模事業では、簿記に明るい人材が“何でも屋”になりがちです。請求書の整理から試算表の作成、そして「申告書のひな型も作ってほしい」という期待へ。そこに、「形式上の代筆」と「法律上の税務書類作成」の違いが見えづらい現実があります。
・記帳=OK/申告書作成=要資格 の周知不足
・属人的に回る実務、チェック・承認フローの不在
・e-Taxやクラウド会計の浸透で「ボタン一つ」の錯覚
数字が示す“境界逸脱”のリスクとコスト
本件のような境界逸脱は、書類送検や罰則の可能性だけでなく、依頼者側にも重い影響(修正申告・加算税・延滞税・資金繰り悪化)を招きます。組織は「可視化されたコスト」と「見えないレピュテーションコスト」を同時に管理する必要があります。
| リスク領域 | 想定インパクト | 予防指標(KPI例) |
|---|---|---|
| 法令遵守 | 書類送検・行政/刑事リスク・行政対応コスト | 税務書類レビュー率100%、税理士押印/電子署名率100% |
| 財務 | 修正申告・加算税等、キャッシュアウト増 | 申告差異率(前年比)、修正申告件数/月 |
| 風評 | 取引先・金融機関の信頼低下、採用難 | 与信スコア推移、主要取引先満足度 |
なぜ“頼れる人”だけが突出して過負荷になるのか?
対立軸の本質は「地域の実務需要」vs「専門家の供給・アクセス」。高齢化や人手不足、依頼者のコスト制約が、“境界の内側”で頑張る人に過剰な期待を集めます。心理的には「いつも助けてくれる人への依頼の延長線上」で、制度理解が後回しになりがちです。
・コスト重視(迅速・安価) ←→ 法令重視(資格・手続)
・地域密着の利便性 ←→ 遠隔の専門家レビュー
・“ついで”の依頼 ←→ 契約書に基づく厳格な範囲管理
「記帳代行は広く認められていますが、税務書類の作成・代理は税理士の独占領域です。
実務の連続性に見えても、法的には明確な分岐点があります。
組織は“レビュー・承認・提出”のどの段階が誰の権限かを文書化し、監査可能にすることが重要です。」
SNSとクラウド会計が生んだ“境界の錯覚”
クラウド会計やe-Taxの普及で、申告プロセスは“触れてみれば簡単そう”に見えます。SNSではテンプレや体験談が拡散され、非専門家でも「できる気がする」心理が醸成されます。しかし、税務は“見えない判断”の積み重ね。入力の一手が法的評価を左右し、のちの調査や修正で大きなコストになることも。
組織はどう動いたのか、そしてどう動くべきか
本件では国税局の告発を受け、警察が捜査、地検に書類送検されました。個別事案の帰趨とは別に、地域・事業者・支援者の三者で“合法の助け合いモデル”を組み直すことが、再発防止の最短ルートです。
- 業務範囲の明文化:記帳(仕訳・残高照合)と税務(申告書作成・提出・代理)の定義を就業規則・業務マニュアルに追記。
- 契約と見積の分離:「記帳委託契約」と「税務顧問契約」を完全分離、請求書も別立て。
- レビュー・承認フロー:税務書類は税理士レビュー100%・電子署名/提出権限は税理士アカウントに限定。
- ログ監査:クラウド会計の操作ログを月次エクスポート、第三者チェックで境界逸脱を検知。
- 教育と周知:社内・取引先向けに「どこから税理士業務か」1枚リーフ(PDF)を配布。
- 地域ネットワーク:近隣税理士との連携窓口を設置、繁忙期のスポットレビュー枠を確保。
よくある質問(FAQ)
まとめ──“境界の可視化”が地域を守る
本件は、地域を支える“善意の実務”が、制度とすれ違った瞬間を映し出しました。読了後のアクションはシンプルです。①業務範囲の文書化、②契約の分離、③税理士レビュー100%、④権限・ログの監査、⑤地域連携窓口の設置。
境界を可視化すれば、頼る側も、支える側も、安心して役割を発揮できます。法の線引きを“壁”ではなく“ガイド”に。その一歩が、地域の経営と税務の健全性を長期で底上げします。