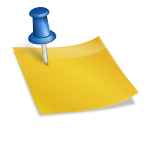日産自動車に再び経営危機の影が落ちています。1999年にカルロス・ゴーン氏が打ち出した「三権分立」の仕組みは、当初は日産の再建を支える象徴的な改革とされました。しかし、その後の変質と崩壊により、収益偏重の経営姿勢が強まり、再び危機に陥ったのです。なぜゴーン時代の遺産は長期的な安定をもたらさなかったのでしょうか。そして今後、日産はどこへ向かうのでしょうか。あなたも疑問に思ったことはありませんか?
- ゴーン時代に導入された「三権分立」が崩壊
- 収益重視が行き過ぎ、車作りの基盤が揺らぐ
- 国内工場停止などリストラが相次ぐ
- 専門家や世論から批判と不安の声が拡大
事件・不祥事の概要(何が起きたか)
日産自動車は2025年、再び経営危機に直面しています。背景には、カルロス・ゴーン時代に導入された「三権分立」の仕組みが形骸化し、収益偏重の体質に陥ったことがあると指摘されています。国内2工場の停止に踏み込むなど、過去の不祥事に続く大規模リストラが行われています。
発生の背景・原因
1999年に来日した当時、日産は巨額赤字に苦しみ、車種ごとの収益管理すらできていませんでした。ゴーン氏は「商品」「収益」「生産」の権限を分割し、責任を明確化することで再建を進めました。しかし、その後の経営陣は収益指標に偏重し、品質や開発力のバランスを欠いていきました。
関連記事
関係者の動向・コメント
現経営陣は「短期的な収益改善を最優先した結果、車づくりの競争力が低下した」と説明。労働組合からは「現場を疲弊させるだけ」との声が出ており、従業員と経営層の溝は深まっています。
被害状況や金額・人数
国内工場の停止により数千人規模の雇用が影響を受け、地域経済にも打撃が広がっています。販売面でも主要市場でのシェア低下が目立ち、年間数千億円規模の売上減が懸念されています。
行政・警察・企業の対応
政府は自動車産業全体の競争力低下を懸念し、支援策を検討。企業としての日産は新たな経営改革プランを発表しましたが、抜本的な解決策になるかは不透明です。
専門家の見解や分析
経営学者は「三権分立は形だけが残り、実態は収益指標を過度に優先した」と分析。また自動車産業アナリストは「短期的な数値に追われた結果、技術投資が後回しになった」と指摘しています。
SNS・世間の反応
SNS上では「またリストラか」「従業員や地域が犠牲になっている」と批判的な声が多数。一方で「ゴーン時代の改革を見直すべき」との意見も見られます。
今後の見通し・影響
今後、電動化や次世代モビリティへの対応を怠れば、国際競争での地位がさらに低下する恐れがあります。日産が再び信頼を取り戻すには、収益と品質のバランスを見直す必要があるでしょう。
FAQ
Q. ゴーン時代の「三権分立」とは?
A. 車づくりにおける「商品」「収益」「生産」の権限を分割し、責任を明確化した制度です。
Q. なぜ収益偏重になったのですか?
A. 数字改善を重視するあまり、品質や開発の重要性が軽視されるようになったためです。
Q. 今後の影響は?
A. 国内外でのシェア低下や雇用問題が拡大する恐れがあり、業界全体への波及も懸念されます。
まとめ
日産はゴーン時代に導入された「三権分立」の崩壊と収益偏重の体質が再び危機を招いています。短期的な収益ではなく、長期的な技術開発や品質維持に舵を切れるかが最大の課題です。企業と社会が一体となって、信頼回復に取り組むことが求められています。