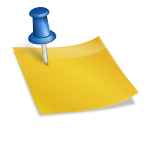「スマホを前提にした社会が生きづらい」——そんな高齢者たちの声が注目されています。
今、飲食店やスーパーではセルフレジやQRコード注文など、デジタル化が急速に進んでいます。しかし、スマートフォンやタブレットに不慣れなシニア層にとって、それは大きな負担となっているようです。
なぜ「便利」の裏側で、行き場を失う人々がいるのでしょうか。あなたも気になりませんか?
スマホ前提の店舗に高齢者の戸惑い
東京都練馬区のスーパーや飲食店では、注文や支払いのスタイルが大きく変化しています。特に目立つのが、セルフレジやスマホによるQRコード注文の導入。
こうした変化により、「操作がわからない」「迷惑をかけたくない」と感じる高齢者の声が多く聞かれるようになりました。
背景にはデジタル化の加速
新型コロナウイルス禍を契機に、非接触型の注文・決済方法が一気に広まりました。東京都内で複数店舗を持つスーパー「アキダイ」でも、2020年以降にセルフレジを導入。
中村橋店の店長によると、初期費用が低く、人件費の削減効果もあるとのこと。しかし、その裏で操作に不慣れな高齢客へのサポートも求められていました。
「スマホなしでは生活できない」現実
81歳の女性は、スマホ注文になったことで行きつけの飲食店に通わなくなったといいます。「紙のメニューがない」「視力が落ちて見づらい」といった理由から、外食機会そのものが減少。
「スマホを持っているのが当たり前」という前提が、高齢者を取り残しているのです。
現場での具体的な工夫と対応
アキダイ中村橋店では、レジ付近に《お釣りをとったらレシートがでます!》という大きな注意書きを掲示。また、セルフレジ導入当初はスタッフが付き添って丁寧にサポートしていました。
こうした人の手による対応が、今も必要とされています。
他業種での芸能・接客業の現状
飲食業界だけでなく、芸能界でも「対面」や「接触」を重視する動きが見直されています。リアルイベントや握手会などの復活が示す通り、人と人のやりとりには代えがたい価値があるのです。
デジタル技術が進化する中でも、“人間らしさ”が求められる場面は確かに存在しています。
SNSでも賛否が分かれる声
X(旧Twitter)では、「高齢者に冷たい社会」「スマホ使えない人に不親切すぎる」などの批判の声と、「効率化のためには仕方ない」「店員減らして値下げしてほしい」などの肯定意見が並存。
世代や生活スタイルによって受け止め方は大きく異なります。
高齢者とデジタル社会の未来は?
高齢化が進む中で、誰もがデジタル機器を使いこなすことは現実的とは言えません。行政や店舗による支援や、多様な選択肢の提供が必要です。
「スマホが苦手」でも安心して外出や買い物ができる社会づくりが、今後ますます重要になっていくでしょう。
- 高齢者がスマホ注文・セルフレジに戸惑い
- 飲食店で紙のメニューが廃止され通えなくなる例も
- 導入店舗側もサポート体制を工夫
- 「スマホ前提社会」に生きづらさを感じる声が広がる
よくある質問(FAQ)
A. 一部店舗では紙のメニューや対面注文も継続しており、選択肢はあります。
A. 人手不足と効率化のため、多くの店舗で導入が進んでいます。
A. 店舗によっては操作サポートスタッフの配置や、紙案内の活用が行われています。
まとめ
スマートフォンを前提とした注文や支払いの仕組みが日常化する一方で、それに対応できない高齢者が取り残される現状が浮き彫りになっています。
便利さの追求と、人間らしいサポートのバランスが求められる今、誰もが安心して利用できる社会設計が必要とされているのではないでしょうか。