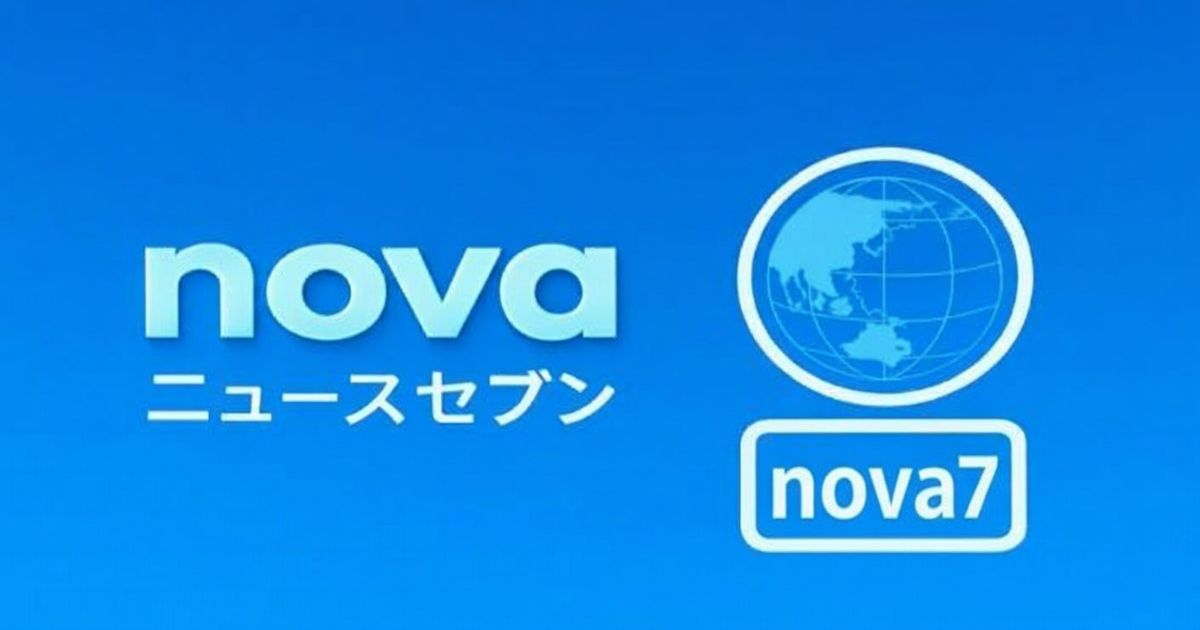「子どもの投げ銭280万円は取り消せるのか?」——2025年8月、そんな問いが現実の裁判になりました。ライブ配信で“応援”が数字になる時代、未成年の一瞬の熱が家計を大きく揺らすことがあります。
京都市の10歳男児が兄のスマホでTikTokのコインを大量購入し、配信者へ投げ銭。約3か月でTikTok分だけで約370万円、他アプリも含めると約460万円に膨張。返金は約90万円にとどまり、家族は運営企業と決済企業を相手取り京都地裁へ——そんな“現代の消費トラブル”が法廷で争われようとしています。
本稿は、出来事の整理から民法の「未成年者取消権」、年齢確認の実務、そして家庭・学校・企業・行政が取るべき具体策まで、感情とデータの両面から立体的に解説します。読み終えるころには、明日からの“予防設計”がそのまま実装できる状態になっているはずです。
- 小学生が兄のスマホで投げ銭、TikTok約370万円/合計約460万円
- 返金は約90万円のみ。残額の返金を求め京都地裁へ提訴(被告:運営会社日本法人/決済企業)
- 未成年者契約の取消権(民法5条)と詐術による制限(民法21条)が主要争点
- プラットフォーム側の年齢・ギフティング制限と実効的確認が問われる
- 家庭×学校×企業×行政の四重予防へ:上限制御・同意設計・金銭教育・ルール化
※報道・解説記事の内容を基に整理(個人名は伏せています)。
| 時期 | 出来事 | 金額の目安 |
|---|---|---|
| 2023年6〜8月 | TikTokでコイン大量購入→配信者へ投げ銭 | 約370万円 |
| 同期間 | 他ゲームアプリでも課金 | 約90万円 |
| 合計 | — | 約460万円 |
| その後 | 消費生活センター相談/返金交渉 | 返金約90万円 |
| 2025年7月9日付 | 京都地裁に提訴(返金約280万円を請求) | — |
返金は一部(約90万円)にとどまり、残額のうち約280万円の返金を求める訴訟に発展。被告はアプリ運営会社の日本法人と、決済を提供した外資系IT企業。
民法5条は、未成年者が法定代理人の同意なく行った契約を取り消せると定めます(未成年者取消権)。一方、未成年者が成年と信じさせるため詐術を用いた場合は取消不可(民法21条)。オンライン決済では入力年齢や同意確認の在り方が焦点となります。
「未成年取消は強力な救済ですが、“詐術”判断や親権者の管理状況、プラットフォームの年齢確認の実効性が絡むと結論は事案により大きく揺れます。
家庭側は承認フローと上限制御、企業側は年齢推定・本人性確認の高度化が同時に必要です」(要旨)
未成年のオンラインゲーム・配信関連の相談は各地の消費生活センターに多数寄せられ、小中高生のオンラインゲーム相談は2022年度で4,024件、平均契約金額は約33万円と報告されています。
| 年度 | 対象 | 相談状況(例) |
|---|---|---|
| 2022年度 | 小中高生(PIO-NET) | ゲーム相談4,024件/平均約33万円 |
| 2024年度 | 全国 | 消費生活相談総数の公開統計あり(継続更新) |
※PIO-NET統計は登録時期等により後日更新される場合があります。
可視化された応援(投げ銭)は、承認欲求や“推し活”と結びつき衝動性を高めます。スマホが個人端末化し、家庭の監督が及びにくい構造に、年齢確認の穴や承認フローの不徹底が重なると被害が拡大します。地方自治体も休暇期の高額課金増を警戒しています。
・家庭:子の自律と保護の線引き/監督義務の実装(パスコード・承認)
・企業:年齢・本人確認の実効性/UIでの抑制設計・上限・返金規程
・学校:金銭リテラシー・情報モラル教育のアップデート
・行政:ガイドライン・周知・統計と被害回復の枠組み整備
TikTokはLIVEギフトの送受信は18歳以上など年齢制限を掲げ、コイン購入は18歳以上(又は成年年齢の高い方)と明記しています。実装の確認精度と不正回避の徹底が鍵になります。
家庭では、iPhoneの「承認と購入のリクエスト」等で課金を承認制に。企業は年齢・本人性確認(KYC/推定AI+証憑)の多層化、上限・冷却期間の導入、返金ガイドの明文化が望まれます。行政は未成年課金の実態把握とルール化をさらに推進中です。
① 端末の生体・パスコードを親管理/決済情報の保存オフ
② App/Play ストアを承認制に(ファミリー共有・ペアレンタル)
③ アプリ内の年齢・ギフト機能の制限を確認
④ 明細の週次チェックと家族ルール化(上限・時間・用途)
⑤ 不審課金はすぐ消費生活センター相談→事業者交渉
未成年の高額課金は、家庭の管理困難×プラットフォームの確認不備×心理設計が重なると発生します。未成年取消権を機能させるには、企業の実効的年齢確認と上限制御、家庭の承認フロー、学校の金銭教育、行政のルール整備を同時に進める必要があります。今日からできる“四重の予防”で、同じ悲劇を繰り返さない社会へ。