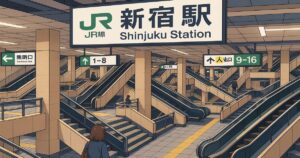共働き家庭にとって「小1の壁」は避けて通れない課題です。保育園時代と異なり、小学校に上がると子どもの居場所や時間割が大きく変化し、親の就業スタイルや家庭生活に深刻な影響を及ぼします。とりわけ「放課後の居場所」「長期休暇中の預け先」などが家庭の頭を悩ませています。
本記事では、調査データや実際の体験談をもとに、小1の壁の実態と背景、親たちが求める働き方、企業や社会の制度的課題を詳しく解説します。柔軟な働き方や支援制度の普及に向けて、読者に役立つ視点を提供します。
- 小1の壁とは何かとその主な要因
- 調査データから見る放課後・長期休暇の課題
- 働き方の変化と親の体験談
- 今後に必要な制度・社会の改善策
小1の壁とは何か?
保育園から小学校へのギャップ
保育園は早朝から延長保育まで対応し、共働き家庭を全面的にサポートしてきました。しかし小学校入学後は、給食が終われば下校というケースもあり、放課後の居場所を確保する必要が生じます。これがいわゆる「小1の壁」です。
・保育園:朝7時台~夜7時以降まで延長可能
・小学校:下校は午後2~3時台が中心
・学童保育:定員不足や時間制限が多い
親の働き方とのミスマッチ
親の就業時間と子どもの下校時間が合わないため、退勤後に猛ダッシュで迎えに行く日常が続きます。このギャップが「息する暇もない」と表現されるほどの負担を生みます。
調査データから見る小1の壁
調査結果の概要
子ども向け写真サービスを展開する株式会社「千」の調査によれば、1,223人の保護者のうち「小1の壁を感じた・感じそう」と答えた人は35.4%。最も大きな課題は「放課後の居場所の手配・確保」で15.9%、次いで「長期休暇の子どもの世話」が14.5%でした。
| 課題内容 | 割合 |
|---|---|
| 放課後の居場所 | 15.9% |
| 長期休暇の世話 | 14.5% |
| 朝の送り迎え調整 | 約10% |
働き方の変化
正社員や契約社員として働いていた人の割合は62.8%から61.1%に微減。一方、派遣やパート勤務は15.3%から17.1%へ微増しました。小1の壁によって「正規雇用から柔軟な働き方へのシフト」がわずかに進んでいる実態が見えます。
親の体験談にみる現実
定時ダッシュと家庭生活の両立
ある40代女性は「息をする暇もない」と語ります。午後5時半に下の子の保育園迎え、6時に学童迎え、帰宅後はご飯とお風呂で夜9時に寝かしつける毎日。会議や残業には参加できず、同僚に負担を頼む場面もありました。
夫婦分担の工夫
PTAや面談を夫が担当するなど、自然な分担を取り入れることで乗り越えられたと振り返ります。また、家事は夫が食器洗いや炊飯器の準備を担当。こうした「夫婦での分担」が支えになったケースです。
制度と社会の課題
時短勤務制度の不足
厚労省調査によれば、育児のための所定労働時間の短縮措置を設ける事業所は74.5%。しかし「小学校入学後も利用可能」な企業は44.5%にとどまります。実際、制度がないために正社員からパートに転職した女性もいます。
性別役割分担の固定観念
「まず母親がなんとかする」という社会的圧力が残り、女性がキャリアを縮小する背景になっています。父親の育児参加率が低いことも「小1の壁」を厚くしている要因の一つです。
・制度の利用期限が短い
・父親の育児参加が限定的
・在宅勤務や時短勤務の活用が進んでいない
よくある質問(FAQ)
Q1. 小1の壁を乗り越えるには何が必要ですか?
A1. 学童保育の拡充や在宅勤務制度の活用、夫婦での家事・育児分担が効果的です。
Q2. 在宅勤務はどのように役立ちますか?
A2. 子どもの送迎後に自宅で仕事を再開できるため、家庭と仕事の両立がしやすくなります。
Q3. 企業はどのような支援が求められますか?
A3. 時短勤務の延長、在宅勤務制度の浸透、長期休暇中のサポート制度などが求められています。
まとめと今後の展望
小1の壁は単なる家庭の課題ではなく、社会全体の構造的問題です。学童保育や柔軟な働き方制度の拡充、父親の育児参加がカギとなります。企業も「育児期間もキャリア形成の一部」と捉え、制度設計を見直す必要があります。
- 小1の壁は「放課後」「長期休暇」の課題が中心
- 正規雇用から柔軟な働き方へのシフトが進行
- 夫婦分担と在宅勤務が負担軽減に有効
- 制度整備と父親の参加拡大が社会的課題