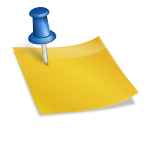ぬいぐるみを連れて出掛ける、写真を撮る、服を着せる。
「ぬい活(ぬいぐるみ活動)」と呼ばれるこのカルチャーが、Z世代だけでなく大人の間でも急拡大しています。
2025年の流行語大賞ノミネートにも登場した「ぬい活」は、単なる趣味の域を超え、 宿泊プランや保育サービスなど新たなビジネスを生み出す一大市場へと成長中。 この記事では、ぬい活がもたらす“静かな熱狂”の背景と、企業が注目する理由を探ります。
「ぬい活(ぬいぐるみ活動)」と呼ばれるこのカルチャーが、Z世代だけでなく大人の間でも急拡大しています。
2025年の流行語大賞ノミネートにも登場した「ぬい活」は、単なる趣味の域を超え、 宿泊プランや保育サービスなど新たなビジネスを生み出す一大市場へと成長中。 この記事では、ぬい活がもたらす“静かな熱狂”の背景と、企業が注目する理由を探ります。
この記事で得られる情報
ぬい活とは?Z世代から大人まで広がる“癒やしの文化”
ぬい活とは「ぬいぐるみ活動」の略で、自分の好きなぬいぐるみを身近に置き、 日常生活を共に過ごす行為を指します。街中ではカバンに小さなぬいを付ける女子高生や、 職場のデスクに“推しぬい”を飾る大人の姿も増えました。 SHIBUYA109エンタテイメントの調査では、ぬい活には「バッグに付ける」「一緒に写真を撮る」 「洋服を購入・手作りする」「寝るときに添える」など多様な形があり、 約6割のZ世代女性が“何らかのぬい活”を日常的に行っていると回答。 ぬいぐるみコミュニケーションプランナー・金子花菜氏は、 「ぬい活は自己表現であり、コミュニケーションのツール」と語ります。 「好きなキャラや“推し”を象徴するぬいと過ごすことで、 自分を投影し、安心感や共感を得る。現代のストレス社会で心の拠り所になっているのです」。市場拡大の背景 “推し活”の延長とSNS文化の融合
ぬい活は、いわば“推し活の進化形”です。 好きなアニメキャラやアイドルのぬいぐるみと共に旅をし、 レストランや観光地で写真を撮ってSNSに投稿する。 「ぬいを通じて推しと過ごす時間」を共有するのが、Z世代の自然な行動様式となっています。 日本玩具協会の統計によると、ぬいぐるみ市場は2024年度に前年比115.3%成長。 特に20代後半〜30代女性の購入率が急上昇しています。 これは“ぬいが映える世界観”を演出するSNS文化の影響も大きく、 InstagramやX(旧Twitter)には「#ぬい撮り」「#ぬい活アカウント」などのタグが急増中です。 さらに、ぬい活は男女問わず広がっています。 男性ファンの中には「出張先でぬいを撮影して癒やされる」「孤独を和らげる存在」と語る人も。 単なるファン文化にとどまらず、心の健康を支える新たな“ソーシャルセラピー”としても注目されています。ぬい活の経済効果 アクスタより儲かる構造とは
金子花菜氏は、企業がぬい活市場に注目する理由をこう語ります。 「ぬいぐるみは原価が安いのに単価が高く設定でき、 アクリルスタンドなどより利益率が高いんです。首から下の規格が統一されているため、 衣装の量産や交換も容易。結果として“コレクション経済”を形成しやすい」。 実際、ぬいの洋服やアクセサリー市場も急成長しています。 ユザワヤや手芸専門店では「ぬいぐるみ専用パーツ」「ぬい服づくりセット」が人気商品に。 自作文化とハンドメイド需要が相互に刺激し合い、関連市場は年間400億円を突破しました。 また、ぬい活に関連した撮影スタジオや保管サービスも増加。 中には「ぬい専用クリーニング」や「修繕リペア専門店」も登場し、 “ぬいを長く愛でる”文化が経済圏を形成しつつあります。ホテルも参入「ぬいとお泊りプラン」が人気
東横インが提供する「ぬいとお泊りプラン」は、まさにこの潮流を象徴するサービスです。 利用者は自分のぬいをホテルに預け、専任スタッフが「滞在中のぬい」を写真撮影。 後日フォトアルバムとして返送してくれるというユニークな宿泊プランです。 「宿泊客本人が泊まらなくてもOK」という点がSNSで話題を呼び、 2025年上半期には予約率が通常プランの1.6倍に。 全国の観光ホテルでも類似サービスが相次ぎ、 “ぬいぐるみ旅行”という新ジャンルが確立しつつあります。 旅行代理店関係者は「人間が移動しなくても“ぬいが旅をする”需要がある。 撮影付きプランは記念品にもなり、ギフト需要も強い」と話します。 この動きはコロナ禍で生まれた“非接触消費”の進化系ともいえるでしょう。ぬい活の心理的効果 「癒やし」と「自己肯定感」の回復
金子氏によれば、ぬい活の魅力は「かわいさ」だけではありません。 「ぬいは、持ち主の心の投影です。仕事で疲れたとき、 “ぬいがそばにいてくれる”という安心感が自己肯定感を回復させる。 現代の人間関係が希薄化する中で、ぬいは静かに“心の居場所”になっています」。 特に注目されるのは、ぬいぐるみを“キャラクター化”する心理。 推しキャラやオリジナルぬいを人格のように扱い、 「おはよう」「いってらっしゃい」と声をかける行為には、 セルフケアやマインドフルネスに近い効果があるとされています。 精神科医のコメントでも「ぬいぐるみを通じた対話行為は、 孤立感の軽減に寄与する」との指摘があり、 メンタルヘルス面からもぬい活が注目されています。大人世代の“ぬいデビュー”が増える理由
中年層でも「仕事帰りにぬいと過ごす」「旅行に連れて行く」など、 “ぬいデビュー”を果たす人が増えています。 背景には、コロナ禍での孤立感や、SNS上での共感文化の広がりがあります。 「Z世代のように発信はしないけれど、 自分の世界でぬいを愛でる40代・50代の層が増えています」と金子氏。 「ぬいは言葉を発さず、否定もしない存在。 だからこそ大人が求める“無言の癒やし”を提供してくれるのです」。 また、親世代が子どものぬいを通じてぬい活を始めるケースも多く、 家族のコミュニケーションツールとしての役割も広がっています。FAQ
Q1: ぬい活とはどんな活動?
A1: ぬいぐるみを身近に置き、持ち歩いたり撮影したりする行為。自己表現・癒やし・推し活の一環として人気です。
Q2: ぬい活市場はどのくらい拡大している?
A2: 2024年度は前年比115.3%増と過去最高を記録。関連サービスを含めると市場規模は1500億円を超えています。
Q3: なぜ大人にも広がっている?
A3: ストレス社会での癒やし需要と、SNSを介した共感文化の拡大が背景。言葉を超えた心の交流が支持されています。
Q4: 企業はどのように参入している?
A4: 東横インの「ぬいとお泊りプラン」など、宿泊・手芸・クリーニングなど多業種が参入しています。
Q5: 今後の展望は?
A5: デジタル連携による「ぬいのAI化」や、メタバース上でのぬい交流など、新しい“デジタルぬい活”の可能性も期待されています。
まとめ|“静かな熱狂”が映す現代の孤独と希望
ぬい活は、誰かに見せるための活動ではなく、自分の心を整える行為。 “かわいい”という感情が共感や癒やしを生み、現代の孤独社会に小さな希望を灯しています。
ビジネス面では巨大市場に成長しつつも、その根底には「人が温もりを求める本能」があります。 ぬいぐるみは、AIやデジタルが進化するほど逆に求められる“アナログな心のパートナー”なのかもしれません。
ビジネス面では巨大市場に成長しつつも、その根底には「人が温もりを求める本能」があります。 ぬいぐるみは、AIやデジタルが進化するほど逆に求められる“アナログな心のパートナー”なのかもしれません。
外部参考情報
[公式発表]:ビジネス+IT「なぜ大人が沼る?『ぬい活』が生む“静かな熱狂”」(2025年11月12日)
[データ出典]:日本玩具協会「2024年度 玩具市場動向」/SHIBUYA109エンタテイメント調査
[関連企業]:東横イン「ぬいとお泊りプラン」公式サイト、ユザワヤ「ぬいぐるみ特集」
[公式発表]:ビジネス+IT「なぜ大人が沼る?『ぬい活』が生む“静かな熱狂”」(2025年11月12日)
[データ出典]:日本玩具協会「2024年度 玩具市場動向」/SHIBUYA109エンタテイメント調査
[関連企業]:東横イン「ぬいとお泊りプラン」公式サイト、ユザワヤ「ぬいぐるみ特集」