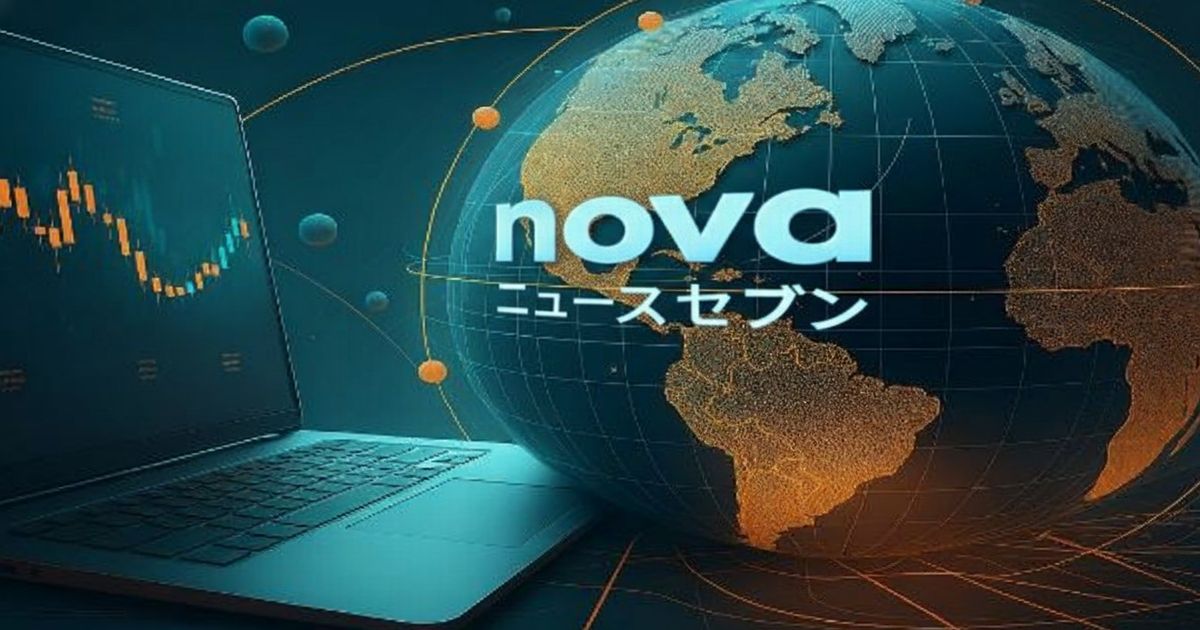茨城県水戸市の常陽銀行で、元行員による不正行為が発覚しました。
60代の男性行員が、クレジットカードの審査権限を悪用し、自身のキャッシング枠を不正に増額して2351万円を引き出していたのです。
この事件はなぜ長年発覚しなかったのか、そして銀行側はどのような対応を取ったのでしょうか。あなたも気になりませんか?
60代の男性行員が、クレジットカードの審査権限を悪用し、自身のキャッシング枠を不正に増額して2351万円を引き出していたのです。
この事件はなぜ長年発覚しなかったのか、そして銀行側はどのような対応を取ったのでしょうか。あなたも気になりませんか?
この記事で得られる情報
ニュース本編:何が起きたのか
常陽銀行は2025年10月24日、同行の元行員(60代)がクレジットカードの審査権限を悪用し、自身のキャッシング枠を不正に増額していたと発表しました。この元行員は2016年から2024年まで、審査手続きを経ずに限度額を上げ、ATMから複数回にわたって現金を引き出していました。不正に増額された総額は1550万円、不正引き出し額は2351万円に上るといいます。
銀行は22日付で懲戒解雇し、県警水戸署へ被害届を提出する方針を示しました。
人物と経歴:元行員の業務と立場
男性は同行営業企画部に所属し、クレジットカードの審査および管理業務を担当していました。行内では信頼を得ていたとみられ、長年にわたり不正を繰り返しても発覚しなかった点が注目されています。職権を利用できる立場を悪用した典型的な「内部犯行」として、金融業界内でも波紋を呼んでいます。
過去の類似事例との比較
金融機関の不正は、地方銀行を中心に近年相次いでいます。2023年には他行で職員による融資データ改ざんが発覚し、内部統制の見直しが全国で進みました。今回の常陽銀行のケースは「個人の不正利用」ですが、監査体制の甘さという共通課題が浮き彫りになっています。
発覚の経緯:カード更新時の異変
事件が発覚したのは、カード更新のタイミングでした。審査部門が通常と異なる増額履歴を確認し、社内調査を実施。2024年9月25日に不正が明らかになり、銀行側が内部調査を経て公表に至りました。全額弁済が確認されたものの、同行は刑事責任の追及を避けない姿勢を示しています。
銀行側の対応と再発防止
常陽銀行は「経営責任および管理監督責任の所在を明確化し、関係者の処分を進める」とコメントしています。再発防止策として、審査権限の多重チェック体制の導入や、AIによる不正検知システムの強化が検討されているとみられます。
要点まとめ
- 元行員が自身のカード枠を不正に増額し2351万円を引き出し
- 不正期間は2016〜2024年、8年間にわたり発覚せず
- 全額弁済済みだが、懲戒解雇処分と被害届提出へ
- 同行は管理体制の見直しと信頼回復に注力
SNSでの反応
SNSでは「内部管理どうなってるの?」「長年バレないのが怖い」といった声が多く寄せられています。一方で、「全額返済したならまだ良心的」「金融機関の信頼は積み重ねが大事」と冷静に受け止める意見も見られます。
今後の展望
常陽銀行は今回の不祥事を受け、行内教育の徹底や監査プロセスの強化を図る見込みです。地方銀行が信頼を取り戻すには、透明性の高い情報公開と顧客第一の姿勢が不可欠です。金融機関全体にとっても、信頼の再構築が問われる時代に差し掛かっています。
FAQ
Q1. なぜ8年間も不正が発覚しなかったの?
A. 審査権限を持つ本人が自分のカード情報を操作していたため、通常の監査では検知が難しかったとみられます。
Q2. 銀行はどのような処分を行った?
A. 男性行員は懲戒解雇処分となり、銀行は被害届を提出。役員などの管理責任についても調査が進められています。
まとめ:
今回の常陽銀行元行員による不正引き出し事件は、内部統制の盲点を突いた深刻なケースでした。
全額弁済が行われたとはいえ、信頼の失墜は大きく、再発防止の徹底が求められます。今後の対応次第で、銀行の透明性と信用力の行方が問われることになりそうです。
今回の常陽銀行元行員による不正引き出し事件は、内部統制の盲点を突いた深刻なケースでした。
全額弁済が行われたとはいえ、信頼の失墜は大きく、再発防止の徹底が求められます。今後の対応次第で、銀行の透明性と信用力の行方が問われることになりそうです。