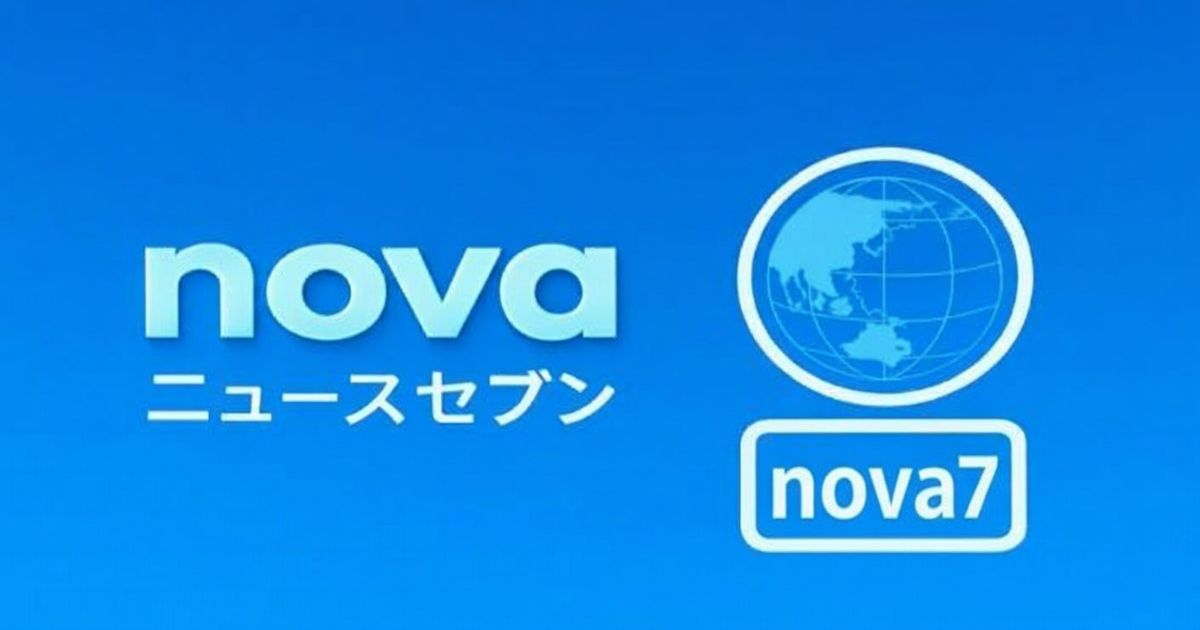かつて新車販売シェアの9割超を誇った日本車が、今タイ市場で揺らいでいます。中国勢の電気自動車(EV)が急速に拡大し、日本メーカーは守勢からの巻き返しを余儀なくされています。
トヨタや三菱、マツダといった大手は、低価格帯のハイブリッド車(HV)を相次いで投入。環境性能と利便性を武器に、かつての「牙城」を守ろうとしているのです。
この記事では、日本車のタイ市場における歴史と現在の苦境、そして未来に向けた戦略を整理し、読者が「自動車産業の地殻変動」を理解できるよう解説します。
- 物語的要素:かつての独占市場で日本車が直面する試練
- 事実データ:2025年、シェア7割割れの可能性
- 問題の構造:中国勢EVの攻勢と値引き戦略
- 解決策:低価格HV投入、現地工場の強化
- 未来への示唆:EVとHVのバランスがカギ
2025年のタイ市場で何が起きているのか?
トヨタは小型セダン「ヤリスエイティブHV」を71万9,000バーツで発売し、従来のHVより1割安く設定しました。三菱もSUV「エクスフォースHV」を投入し、ヤマハとの共同開発オーディオで若年層を狙います。マツダは2025〜2027年にかけてHV・EVを5車種展開予定です。
すべては「圧倒的シェア」から始まった
2010年、日本車のシェアは92.3%に達し、2011年以降も80%台後半を維持しました。しかし2023年、政府のEV振興策を契機に77.8%まで急落。2024年上半期には70.6%にまで落ち込みました。
数字が示す日本車苦戦の実態
| 区分 | 2023年上期 | 2024年上期 |
|---|---|---|
| 日本車シェア | 77.8% | 70.6% |
| 中国車シェア | 約10% | 16%超 |
| BYDシェア | ― | 7.8% |
なぜ中国EVだけが急拡大するのか?
中国メーカーは政府補助金を背景に、大幅な値引き攻勢を展開。BYDの「ドルフィン」は発売から1年で約3割値下げされ、49万9,900バーツに。手軽な価格設定が購買層を一気に広げました。対する日本勢はHV重視の姿勢が強く、戦略のずれが浮き彫りになっています。
SNS拡散が生んだ購買行動の変化
中国メーカーはSNSを駆使したプロモーションで若年層を取り込み、日本車の伝統的な販売網を脅かしています。値引き情報の拡散は消費者心理を大きく動かし、短期間でシェアを奪う原動力となりました。
タイ政府のEV推進策と日本車の課題
タイ政府はEV生産拠点化を国家戦略と位置付け、補助金と税制優遇を拡充。これに対して日本メーカーは現地生産のHV強化にとどまっており、戦略の立て直しが急務となっています。
まとめと展望
日本車はタイ市場で苦境に立たされていますが、低価格HV投入などで巻き返しを図っています。しかし、EV市場の拡大を無視することはできず、両輪戦略が求められます。かつての「牙城」を守れるかどうか、日本メーカーの真価が問われる局面です。