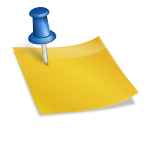「鉄道の未来は地域と共にある。」もしそう語られたら、あなたはどれほど現実味を感じるだろうか。地方の多くの鉄道路線は赤字に苦しみ、やがてバス路線やタクシーに置き換えられる運命だと言われる。しかし、この流れに抗うように、新潟の山中を走る一本の「トンネルだらけの鉄道」がユニークな挑戦を続けている。
その鉄道の名は「北越急行ほくほく線」。かつては首都圏と北陸を結ぶ高速特急「はくたか」を走らせ、第三セクター鉄道の成功モデルと呼ばれた。しかし新幹線開業でその収益基盤は崩壊し、経営難に直面。そんな中で誕生したのが、終電後に鉄道ファンをトンネル探検に連れ出す「ナイトタートル」という過酷ツアーだった。
本記事では、北越急行の歩みと現在、そして彼らが挑む過酷ツアーを通じて、鉄道と地域が生き残るための未来像を考える。読み終える頃、あなたは「地方鉄道の存在意義」について新たな視点を抱くはずだ。
関連記事
- 物語的要素:トンネルを歩く真夜中の探検が誕生した背景
- 事実データ:ほくほく線の赤字決算や内部留保の推移
- 問題の構造:「ドル箱特急」の消滅で失った収益基盤
- 解決策:観光ツアーや映像列車「ゆめぞら号」など新しい挑戦
- 未来への示唆:鉄道単独ではなく地域全体の公共交通ビジョンが必須
深夜に現れた探検列車「ナイトタートル」とは?
2025年7月5日午後11時40分。新潟県南魚沼市・六日町駅のホームに、特別列車「ナイトタートル」がゆっくりと滑り込んだ。眠る町を後にする参加者たちは、夜を徹してトンネルを歩く旅へと向かった。まるで子どもの頃の秘密基地探検を大人になって再現するような体験。定員の2倍以上の応募、抽選で選ばれた23人が鉄路に降り立つ姿は、鉄道への愛情そのものを映し出していた。
旅はまず美佐島駅で下車し、赤倉トンネルへ。普段は入れない非常口や旧変電所を見学した後、しんざ駅に向けて冷気漂う2.2キロの闇の中を歩いた。その後は鍋立山トンネルにも立ち入り、工事の苦労を肌で想像する。最後に夜明けの光を浴びながら、ゆっくりと走る列車に揺られて六日町へ戻る――。単なる観光ではなく、「鉄道が消えようとしている現実を身をもって体験する旅」でもあった。
ほくほく線の歩みは「ドル箱」と共にあった
北越急行ほくほく線の開業は1997年。上越新幹線「越後湯沢」と北陸本線をつなぐ陰の大動脈として誕生した。当初からJRと共同で運行した特急「はくたか」は、東京—金沢を結ぶ最速ルートとして人気を集め、年間数百万人を輸送。開業以来、黒字経営を続けた数少ない第三セクター鉄道として脚光を浴びた。
しかし2015年、北陸新幹線が金沢まで延伸するとすべてが変わった。新潟から北陸へ向かう主要ルートは新幹線に取って代わられ、「はくたか」は姿を消した。収益の9割を占めた列車を失ったことは、ほくほく線にとって生命線を絶たれることに等しかった。
数字が語る経営の苦境
2024年度の決算では、最終損益で8億2045万円もの赤字。2015年以降で最大の悪化である。最盛期に130億円あった内部留保は、75億円とほぼ半減。以下に主要な財務推移を整理した。
| 年度 | 最終損益 | 内部留保 |
|---|---|---|
| 2014年度(新幹線開業前) | 黒字(数億円規模) | 約130億円 |
| 2015年度 | 赤字転落 | 約120億円 |
| 2020年度 | 赤字約5億円 | 約95億円 |
| 2024年度 | 赤字8.2億円 | 75億円 |
数字は冷酷に現実を突きつける。鉄道は安全維持のため莫大な固定費を要するため、単純なコストカットでは解決できないのである。
なぜここまで厳しい現実なのか?
その答えは「鉄道の特性」にある。道路であれば維持管理にかかる費用を利用者数で分散できる。しかし鉄道は線路の点検・車両の保守に一定の人員と設備が不可欠で、利用者が減ったからといって最低ラインを削ることはできない。また通学利用が中心となれば、平日の朝夕以外には乗客が激減し、収益構造が極端に偏る。
「鉄道は社会インフラであると同時に公共財の性格を持ちます。そのため単純な収益論に基づく存続・廃止ではなく、地域全体の交通政策の一環として議論されるべきです。」
SNS拡散が支えるファンの動員
ナイトツアーの人気には、SNSの存在も大きい。暗いトンネルを照らすヘッドライトの光、早朝にホームに戻る達成感――そうした写真や動画が次々と投稿され、「鉄道好きでなくても体験してみたい」と反響を呼ぶ。地方鉄道のイベントは、SNS時代における「観光資源」として新たな価値を持ち始めている。
地域と鉄道をつなぐ解決の糸口
北越急行の取り組みは、単なる知恵比べではない。鉄道を「地域と共に生きる存在」へと変える努力だ。
・ゆめぞら号:車内に映像を投影し、列車を走るプラネタリウムに変える
・トンネル探検ツアー:終電後の線路を舞台に特別体験を提供
・地域イベント連携:沿線の祭りや観光と結びつけた利用促進
だがその一方で、県レベルでの公共交通政策の青写真も不可欠だと指摘される。鉄道単独では解決できず、バス・タクシーを含めた全体像の中で「どの路線を守り、どう活用するか」を議論する必要がある。
未来へ:鉄道と地域が共に生きるために
冒頭で紹介した「ナイトタートル」の参加者は、トンネルを歩きながら「鉄道を守る意味」を身近に感じたという。単なる交通機関ではなく、地域の文化と生活を形作る存在。それこそが鉄道の本質だ。数字だけを見れば赤字の路線。しかし見方を変えれば、地域をひとつに結ぶ「公共の血脈」である。
今後の方向性は明確だ。地域とともに利用を生み出し、観光と生活を両立させる。そして鉄道単独ではなく「交通まちづくり」として公共交通を再設計すること。困難な道である。しかし夜明けの光を浴びる「ナイトタートル」のように、ゆっくりと、確実に新しい未来を走り出すことはできるはずだ。